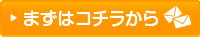重症なら申請すればもらえますか?または難病指定されている病気ならもらえますか?
障害年金はいくつかの要件があります。それを満たしていると認定されてはじめて受給することができます。難病指定されていても、要件を満たさなければもらえません。
要件とは、初診日の状況、保険料の納付状況、障害の程度のほか、初診日に関する病院の証明または関連書類の有無、カルテの有無などが影響します。
ほとんどの場合有期認定となり、数年ごとに診断書を提出して都度審査を受けることになります。認められると、また次回の診断書提出年月が知らされます。
審査により、症状が軽くなったとして、年金が停止したり、等級が変わることもあります。
停止していても原則65歳までは受給権は消滅しませんので、再度診断書を提出して審査を受けることも可能です。
また、その処分に不服があるときは不服申立ても可能です。
あまり多くはありませんが、切断での症状固定や一定の最重度の知的障害等で
以後審査を受ける必要のない永久固定の認定もあります。
就労=停止 ということではありませんので、引き続き障害年金を受給することになりますが、次回診断書提出して審査する際、就労していることで障害の程度が軽くなったと判断されることはあり得ます。その結果、等級が変更し、障害年金の支給が停止されることはあります。
先天性の病気で障害基礎年金を受給していますが、就職して厚生年金に加入しました。今後は障害厚生年金になるのでしょうか。
いいえ違います。障害年金の種類は、その病気の初診日に加入している年金制度によって決まります。先天性や20歳前に初診日がある場合は、障害基礎年金となります。
その後、就職、退職などによって受給している障害年金の種類が変わるわけではありません。
ちなみに、障害年金を受給していても、厚生年金に加入した場合は厚生年金の保険料は納付しなければなりません。退職して国民年金に変わった場合は、受給している障害年金が1級または2級の場合は、国民年金の保険料は法律上当然に免除になりますが、3級の場合はなりません。
ただし、その場合でも前年収入が基準より少ないのであれば、申請して免除を受けることができる場合がありますので、住所地の市町村の国民年金の窓口で確認しましょう。
65歳以降に障害年金の請求をしても、受給できるケースもあります。 保険料納付要件を満たすことは当然ですが、 年金加入中に初診日があり、障害認定日(原則として初診日から1年6ヵ月後)に一定の障害の状態にあり、障害認定日~3ヵ月以内の診断書やその他必要な書類が揃えることができれば、65歳を過ぎても 障害年金の申請をすることはできます。
次の場合は、65歳誕生日の前々日までに申請しなければ、障害年金の対象になりませんので、 注意が必要です。
・障害認定日には障害の状態が軽かったが、その後悪化してしまったケース。
・それほど重くない障害状態であったが、別の病気や怪我が原因でさらに障害状態になってしまい、以前の障害と新たな障害を併せると、重い障害状態になってしまったケース。
1982年(昭和57年)1月1日から、年金加入の国籍要件は撤廃されました。よって、日本に居住する外国籍の方も原則として日本の年金制度に加入しなければなりません。 日本人と同様に、受給資格要件をみたせば老齢年金をもらうことができますし、日本での事故で思いもよらぬ障害を負ってしまった場合などに障害年金の対象になる場合もあります。
年金の受給要件を満たさず短期で帰国する場合、6ヵ月以上の加入があれば、加入期間に応じて「外国人脱退一時金」を請求できます。これは、出国後2年で時効になりますので、注意が必要です。
また、外国企業から日本に赴任する外国籍の会社員等は、自国と日本との年金協定によって、日本の年金制度加入を免除される場合や、日本と海外の年金加入期間の通算ができる場合もあります。 国によって年金協定の内容は異なります。
= 弊事務所では、障害年金・遺族年金・老齢年金の個別相談もお受けいたします =
労務Q&A
採用した社員が初めの1週間で3回遅刻をしてきました。この先が思いやられると思い採用取消したいのですが、問題ないでしょうか?
試用期間中の場合であって、雇入れから14日以内の場合は、解雇予告や解雇予告手当なしで解雇することができます。
就業規則や雇用契約書において試用期間の定めがあり、雇入れから1週間しかたっていないのであれば解雇可能です。
なお、余計な争いを避けるため、試用期間から本採用しない場合の事由についても就業規則に細かく定めておくとよいでしょう。
電車が遅れたといって社員が大幅に遅刻してきました。この場合、遅刻時間について給与を払うのでしょうか?
賃金は労働の対価なので、基本的にノーワークならノーペイで問題はないのですが、それが就業規則や給与規程に明記されていれば明確な根拠となります。このように交通機関の事情による場合や悪天候で通勤が困難な場合などについてどうするかについても就業規則や給与規程で明確にしておくことを勧めます。
ある社員が昇格して管理職となりましたが、その直後から欠勤が増えたり、就業中も何度もトイレに行ったり、またちょっとしたことにすごい勢いで怒ったりと、様子がおかしいのです。「何かあったのか?」と聞いても「なんでもありません。」と答えるだけなので、それ以上なにも聞けないのですが、このままでよいのでしょうか。
仕事内容や責任の変化に伴い、ストレスを抱えることもあります。周囲からみてもおかしいと思う状態が続いているのであれば、じっくりと時間をとって面談をする機会などを持つことを勧めます。
本人は気づいていなくても、治療が必要な程の状態である場合もあります。
長時間労働の有無や健康診断の結果、職場において何かトラブルがないか、また、仕事以外の心配事なども立ち入り過ぎない程度に聞いてもいいでしょう。
事業主は職場や社員に対して安全配慮義務というものあります。ほうっておいて、何か起こった際には、事業主責任を問われることもあります。
100時間を超える長時間労働や、職場内のいじめパワハラセクハラ、大きな仕事のミスや変化などが原因となって精神障害を発症したとなると、労災とされることもあり、そうなると民事損害賠償の請求をされるリスクも高まります。
そのようなリスクを回避するためにも、早期にしっかりと対応しましょう。
また、面談を行った場合は、日時や内容、指導したことなど議事録を作成しておきます。
= 弊事務所では就業規則や付属規程の作成をいたします =
その他Q&A
法人ではなく、個人事業で起業する予定です。 自分の他にはスタッフが3名ですが、健康保険と厚生年金に加入することはできますか?
スタッフ(従業員)の半数以上の同意があれば、認可を受けてスタッフ全員で社会保険に任意加入することができます。その場合、個々のスタッフごとに加入するかしないかを選択することはできません。 また、個人事業主は社会保険に加入できませんので、スタッフが社会保険加入でも、個人事業主だけは「国民健康保険・国民年金」へ加入となります。
会社が加入しなければならない保険ってどういうものがあるのですか?
会社を設立した場合、次のような加入義務があります。
・従業員なしで社長一人の場合でも→ 健康保険・厚生年金保険 加入
・従業員(社員、パート、アルバイト等)が一人でもいる場合
→ 労災保険 加入
→ 勤務状況に応じてさらに雇用保険・健康保険・厚生年金保険 加入
= 弊事務所では会社設立時や、要件に該当した際の各種保険の加入書類の作成から届出まで代行いたします =